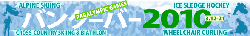2月14日から6日間にわたって、富沢クロスカントリースキーコースで開催されたIPCクロスカントリースキーワールドカップ旭川大会。IPC(国際パラリンピック委員会)が主催するワールドカップは、年に3〜4カ所を転戦することになるが、今回アジアでは初の開催となった。19日に閉幕した大会で、日本はベテラン新田佳浩(日立ソリューションズ)の銀メダル1個、19歳・阿部友里香(日立ソリューションズJSC)の銀メダル3個を含む計9個のメダルを獲得。獲得メダル数21個のロシアや金メダル9個の米国と比較すると、世界で戦える選手不足が浮き彫りになったものの、1998年の長野パラリンピック以来となる日本での国際大会とあって選手、関係者、そして地域の人たちにとって意義のある大会になった。
手応えと課題を得た地元開催
バンクーバーパラリンピック2冠の新田は、15日の男子立位スプリント・クラシカルで2位、16日の同ロング・クラシカルで3位になり、表彰台に上がった。だが、左のかかとのケガで1月の世界選手権(米国・ケーブル)を回避し、今季のメインを今大会と位置づけていたため、笑顔は少ない。
旭川は毎回、パラリンピック前の最終調整を行う特別な地でもある。「負けられない場所だった」と唇をかんだが、最後は「冬のパラスポーツは旭川から発信したい。ここから、もう一度パラリンピックのメダルを目指す」と誓った。
一方の女子立位は、今季好調の阿部が、得意のスプリントなどで連日の表彰台。ソチパラリンピック後にトリノ&バンクーバーパラリンピックのメダリスト、太田渉子氏が引退し、女子のエースと期待される存在だ。
「ソチでパラリンピックの大きな舞台を経験したので、緊張はもうない。十分に練習ができていないけれど、1年前のビデオと見比べると技術面で少し成長できたかな」とは本人談。出場選手が4人と少ないカテゴリーながら、自身初となるワールドカップのメダルを手にし、手応えを得たようだ。
それでも、3年後に迫る18年平昌パラリンピックへの道は険しい。日本代表チームの荒井秀樹監督は「日本で開催したから、14歳の星澤克、13歳の川除大輝(オープン参加)が初めて国際大会を経験できた。それはうれしい話だけれど、シット(座位)とブラインド(視覚障害)のカテゴリーについては選手がおらず、再構築しなければならない」と長年の課題である選手発掘について言及した。
低い大会認知度、求められる街ぐるみでの取り組み
さて、今大会の最も大きな財産は、日本人、特に子どもたちが世界の滑りを自分の目で見たことだ。大会期間中に荒井監督とフランスチームが旭川市立神居東小学校を訪問したことがきっかけで、子どもたちの観戦が実現した。
学校訪問では、全盲のアントニー・シャロコン(フランス)がバイアスロン競技の射撃を20発、的に当てて見せたそうで、「すごくかっこよかったんだよ」と、観戦に来た5年生男児が筆者に興奮気味に語ってくれた。大会に出場した9カ国の国旗を手に、力いっぱい声援を送って大会を盛り上げた子どもたち。ソチパラリンピック金メダリストで視覚障害のブライアン・マキーバー(カナダ)は、「子どもや家族連れの声援が選手の力になったと思う。コースも雪質も良いし、旭川は最高だね」と話していた。
とはいえ、観客数は平日200人、休日でも550人と決して多くはなかった。「スプリントなどは街中で行い、自然に人目に触れる工夫があるいい」とはソチパラリンピック日本代表の佐藤圭一(エイベックスホールディングス)。無料のホットドリンクコーナー、障害によるレースの特性を分かりやすく解説する会場アナウンスなどの工夫はあったが、街中での大会認知度は低く、市を挙げて集客する必要があっただろう。
継続的な国際大会の開催が東京2020成功のカギ
「パラスポーツの大会が日本で開催されることは今まであまりなかった。旭川が開催したことで、日本で行われる夏季競技の大会が多くなることを期待したい」とは、車いす陸上選手の廣道純(プーマジャパン)。今大会をパラスポーツ全体の盛り上げにつなげようと、ソチパラリンピックのバイアスロン(座位)銅メダリストで車いすマラソン選手の久保恒造(日立ソリューションズ)に誘われ、2種目に出場した。
「日本も国際レースを当たり前のように誘致していくべき。僕ら選手はいつも海外に出て行くばかりなので、日本で迎え撃つ経験を増やしていきたいし、なにより海外からトップアスリートに来てもらうことで観客のスポーツを見る目が養われるのではないか」と話し、それが東京パラリンピックの準備に重要だという。
例えば、34回の歴史を刻む大分国際車いすマラソンが参考になる。大分市では、子どもたちが当たり前のように車いすマラソンを観て育ち、市民にとって車いすレーサーが走る姿は当たり前の光景になっていると聞く。
子どもたちだけではない。旭川大会を約200人のボランティアが支えたが、その多くが障がい者スポーツを初めて観た人たちだった。今後、大会が継続的に開催されれば、市民にとって障がい者スポーツが身近なものになるのではないだろうか。
平昌パラリンピックの事前合宿誘致も行う旭川市の富沢クロスカントリースキーコースは、年末年始の時期になると五輪、パラリンピック、ジュニア・ユース世代の日本代表、そしてお年寄りから子どもまでが入り交じってクロスカントリーをしている光景があるという。
それぞれの地方自治体が国際大会を誘致し、それを継続させることが、東京パラリンピック成功のカギを握るのかもしれない。
(取材・文/瀬長あすか、吉村もと)
※この記事は、『Sportsnavi』からの転載です。