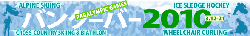重度脳性まひや四肢の重度機能障がいがある人向けに考案された”ボッチャ”。ジャックと呼ばれる目標球に、いかに自分のボールを近づけるかを競うスポーツだ。障がいによってボールを投げるなどの動作が難しい場合は、「ランプ」と呼ばれる勾配具を使用し、競技アシスタントのサポートを受け投球できる。
もっとも障がいが重いBC3クラスの競技アシスタントとして、リオの舞台に立ったのは、大西遼馬さん(滋賀県脊髄損傷者協会障がい者サポートセンタースマイルフレンズ)。13日から始まった個人予選に高橋和樹選手(自立生活センターくれぱす)と挑んだ。
ちなみに、高橋選手は口頭で指示を出すが、発語ができない選手は視線や眉毛の微妙な動きなどで指示するため、選手とアシスタントのコミュニケーションもこのクラスの見どころのひとつと言える。
大西さんは、高橋選手の指示を受けながら、ボールの種類や順番、投げる強さや音など、限られた情報から試合を「想像」する。そして、そこから選手がやりたい展開をイメージしていくそうだ。
リオの初戦では、ポルトガルの選手を相手に第1エンドで3点を先取。続く第2エンドでも1点を追加した。その後、相手に2点を取られたが、4-2で逃げ切った。続く2戦目は世界ランク8位のイギリスの選手と対戦。第1エンドの最後の一球をジャックにピタリと寄せ、3点を入れた。しかし、第2エンドで2点を返されると、第3エンドでわずかに投球が狂い2失点。最終エンドでも追加点を入れられ、3-5で敗れた。予選敗退が決まり、高橋選手は「(ミスが出た)第3エンドを取らなきゃいけなかった。相手の実力のほうが上だった」と悔しさを滲ませた。
ランプを使う場合、難しいのが投げるより「転がす」ボールだという。ボールを離す角度や床の材質などで球筋に違いが表れやすく、しかも同じ会場でもコートによって転がり具合が異なる。リオではこの感覚を掴むことに苦労した。
「試合の中で修正しましたが、なかなかうまくいきませんでした」と大西さんは振り返った。
高橋選手と大西さんの出会いは、偶然だった。高校卒業後、大西さんは鉄道車両メーカー勤務を経て、青年海外協力隊員としてジブチ共和国の職業訓練学校に赴いた。帰国後、埼玉大で学びながら、障がい者の生活をサポートする福祉施設で働いていた時、そこでたまたま高橋選手と知り合った。
高橋選手は、柔道で頸椎損傷の大けがを負い、胸から下の感覚を失った。ちょうど「自分に勝負としてできること」を模索していた時期で、ふたりで地元の名門・埼玉ボッチャクラブを見学。大西さんは高橋選手の生活介助に関わりながら、競技に取り組むようになった。
昨年の今頃は競技を学ぶ途中で、まだ「ボールはどれも丸だから同じように転がると思っていた」(大西さん)。そこから、他の選手のランプや戦術を見て少しずつボールの特性を学び、コートにメジャーを置いて繰り返し投げ、安定したボールの距離感を探し続けた。
ここから先の歩みは、実に鮮烈だ。ストイックに自分たちのプレーに集中する日々を過ごすうちに、どんどん上達していった。試合で対戦する相手はすべて格上にも関わらず、日本選手権の予選会を突破。続いて昨年12月の本大会で見事優勝したことで、「高揚感を感じる間もなく」今年3月の世界選手権(北京)へのエントリーが決まった。そのうえ、初出場ながら銀メダルを獲得したのだからあっぱれだ。
急成長で階段を駆け上がり世界を驚かせたふたりだが、この時、「リオは全く考えていなかった」(大西さん)。実は、世界選手権の翌月には大西さんが仕事の関係で埼玉から滋賀に引っ越すことが決まっており、高橋選手には新しい競技アシスタントと組んで競技を続けるという選択肢があった。
だが、ふたりで組んだ世界選手権の結果でランキングが上位に入り、リオ行きが決まったことで高橋選手は、「やっぱり一緒にやってくれる?」と声をかけたという。
「誘ってくれたことがうれしくてOKと即答しました」と大西さん。再びタッグを組むことになったふたりは、そうしてリオの表彰台に目標を定めることになったのである。「濃厚な1年間でした」。大西さんの言葉に実感がこもる。
大西さんは自身の経験から、競技アシスタントの魅力をこう話してくれた。「緻密な戦略はボッチャならでは。障がいの重い選手の考えや意図から、何をやりたいのかを理解し、表現することが役割のひとつ。そこにやりがいを感じますね」
リオは2試合を戦い抜いた。「ボッチャや競技アシスタントが注目されればうれしい」と大西さん。帰国後もこの経験も生かし、競技に関わっていくつもりだ。
(取材・文/荒木美晴、撮影/吉村もと)
※この記事は、『Sportiva』からの転載です。