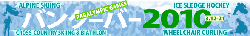平昌パラリンピック最終日の3月18日、江陵ホッケーセンターではパラアイスホッケー決勝が行なわれた。開場が満員になったそのカードは、ともに優勝候補のカナダ対アメリカ。試合は最終ピリオドの終了直前に同点に追いついたアメリカが、延長戦で決勝ゴールを決め、金メダルを手にした。これでアメリカはパラリンピック3連覇を達成。カナダは2006年トリノ大会以来の金メダル獲得はならなかった。
出場8チーム中、アメリカとカナダの実力は突出しており、どちらも1次リーグ、準決勝を圧倒的な強さで勝ち上がった。世界のパラアイスホッケー界の双璧が、そのプライドをかけて戦った決勝は、個々の高い技術に裏打ちされた戦術、最後まで諦めない粘りやメンタルの強さが存分に発揮されていた。世界一を決めるにふさわしい、「これぞホッケー」という試合を観て、パラアイスホッケーの魅力に気づいた人も多かったのではないだろうか。
一方、2大会ぶりに出場した日本は、5戦全敗で最下位の8位に沈んだ。強化してきた守りのシステムが機能した場面もあったが、焦りからレシーブやパスのミスが多発。そこからポジションが崩れ、失点を重ねた。初戦の韓国戦で5人対3人のパワープレーという絶対的チャンスがありながら攻め切れなかったシーンが物語るように、得点力不足は深刻すぎる課題だ。
日本チームの登録17選手のうち半数がパラ初出場ながら、平均年齢は「41.9歳」と高く、大会前からその話題が取り沙汰されていた。人材不足のため、ベテランが踏ん張り、また一度は代表を引退していた選手たちが復活した背景もある。この平均年齢の数字は、国内で競技の灯を消さぬよう、またパラで勝つために努力と夢をつないできた彼らの功績を示すものでもある。
ただ、現実を見ると、その経験値を生かしたプレーができたのは、下位チームが集まる世界選手権Bプールや平昌パラの最終予選まで。世界トップが集まるパラリンピックでは、通用しなかった。スケーティングやハンドリング、視野の広さ、戦術の理解力と実践力、メンタル面、そしてアスリートとしての意識……。結果を見る限り、他国との間に開きがあったと言わざるを得ない。日本代表の中北浩仁監督は「これが実力。すべて私の責任」と肩を落とした。
個人レベルで見ていくと、海外チームには日本の平均年齢より「年上」の選手たちが意外といる。スウェーデンには、ゴールキーパー以外にフォワードにも50代中盤の2選手がエントリーし、日本に勝って7位の成績を収めている。また、ノルウェーのペデルセン(DF)は48歳ながら高い突破力と威力抜群のシュートが持ち味で、日本戦でハットトリックを決め、勝利に大きく貢献している。それぞれ滞氷時間の差はあるにしろ、彼らが年齢に関係なく高いパフォーマンスを見せたことは特筆しておきたい。
日本が海外勢のスピードとパワーに対応しきれなかったのは、”試合勘”の不足が一因と言える。パラ直前には長野での国際大会やイタリア遠征で、韓国、チェコ、ノルウェー、アメリカと対戦しているが、重要なのは年間を通して継続的に格上との海外マッチを組むことだ。
日本は前回ソチ大会の出場を逃したことで、その機会を逸した。時を同じくしてバンクーバー大会よりも世界の競技レベルが一段階上がり、さらにソチまでの4年間は新興勢力のロシアが伸びて、日本とトップレベルとの差は開くばかりだった。
陸続きで移動しやすいヨーロッパや北米は、強豪同士で試合が組める。そんな中、わざわざ長距離移動をして格下の日本にまで足を運ぶ必要はない、というのが本音だろう。その点は同じアジアの韓国にも言えることだが、韓国にはパラリンピック開催国というアドバンテージがあった。彼らはそれを存分に生かし、強豪国との試合を繰り返して強化に励み、銅メダルという形できちんと結果を残した。
来年の春、世界のトップが集まる世界選手権Aプールが開かれる。この大会にはBプールから返り咲いた日本も出場し、アメリカやカナダをはじめ、今回のパラリンピック上位チームと対戦する。ここで下位になると、再びBプールに降格することになり、強豪国との差はさらに開いてしまう。それだけは避けたいところだ。
また今後は、これまでチームがなかった中国の存在も視野に入れなければいけない。次回の冬季パラリンピックは北京が開催地だからだ。中国の情報は今のところ少ないが、08年夏の北京パラリンピックの時がそうであったように、国をあげて選手を集め、チーム強化をすると考えられる。そうなると日本の立ち位置は、いよいよ厳しくなってくる。
喫緊の課題である「世代交代」を進めながら世界に立ち向かうのは容易ではないが、まずは来年の世界選手権で多くのことを吸収し、平昌でリスタートを切った日本復活の足がかりになることを願っている。
(取材・文:荒木美晴、写真:フォトサービス・ワン/植原義晴)
※この記事は、『Sportiva』からの転載です。