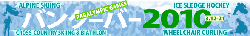めざすは「金メダル獲得!」/撮影:吉村もと=国内最終合宿、軽井沢風越公園アイスアリーナ
「トリノまではあまり思わなかったけど、この4年間は本当に早かったな……」
日本代表の中北浩仁監督は、トリノからの怒涛の4年間を振り返った。先月下旬、国内最終合宿でインタビューしたときのことだ。少し遠くを見つめるその表情には、「やっとここまで来た」という安堵感がにじんでいた。
中北ジャパンのこれまでの軌跡は、棘の道そのものだった。監督に就任したのは、2002年のソルトレークシティパラリンピック後にさかのぼる。
アイスホッケーの土台がない選手たちに、本場カナダ、アメリカで選手として腕を磨いた経験者ならではの技術と戦術を、基礎から教えた。たとえ練習であっても、少しでも気を抜いたプレーをすれば、スティックをへし折るほどの迫力でゲキを飛ばし、勝利にこだわるアスリートとしてのプライドを植えつけた。さらに、ホッケーに集中できる環境を整えるために、勤務先の日立製作所とグループ会社からの資金援助も取り付け、トリノを目前に控えたころには「メダル候補」として外国勢にマークされるまでの存在になった。
しかし、結果はまさかの5位と惨敗。心身のバランスが取れていなかったこと、調整が早すぎたことなど、勝負する以前の問題に直面し、チームは崩壊。結果を出せなかったことで当然、周囲から大きな批判を浴び、「やり方があわない」と、監督のもとを離れていく選手も少なくなかった。当時の心境を、「毎晩、夢に出てくるくらいの重圧だった」と語る。
心を奮い立たせた代表への思い

バンクーバーパラリンピック開会式当日の練習で選手に指示を出す中北監督=UBCサンダーバードアリーナ
ようやく新たな体制のもとで再スタートが切れたのは、代表として何も活動しないまますでに1年が経とうとしていたころだ。すでにバンクーバーに向けて始動している海外チームとの間にできたこの1年の差が、どれほどの向かい風になるのか想像もつかなかったが、中北監督は周囲の反対を押し切り、再びリンクに立つことを決めた。
なぜ、そうまでしてチームに戻るのか、と尋ねたことがある。すると、中北監督はこう応えた。「確かに結果が出せなかった。でも、僕は彼らの力をやっぱり信じているんです」。その背中を押したのは、選手が持つ”可能性”だった。
トリノで終わることは簡単だった、と中北監督は言う。「でも、後任の監督が入ったとしても、その人がホッケーを知っていれば知っているほど、やはり同じことを繰り返してしまうだろうと思いました。それでバトンを渡すのは、無責任だと感じました」
こうして、もう決して後戻りはできない最後の戦いがはじまった。監督の考えに理解を示す選手やスタッフが集まり、遅れた分の時間を取り戻すかのように、代表のトライアウトと強化合宿を重ねた。また、得意の英語を活かして、アメリカやノルウェーなど強豪国の首脳陣に交渉し、海外遠征や招待試合をスケジュールに組み込み、試合勘を養うことにも力を入れた。
数々の試練を乗り越えた先に見えるものは

09年世界選手権のようす。予選で2勝し、バンクーバーパラリンピックの出場枠を決めた=チェコ・オストラヴァ
だが、本当の苦しみを味わったのは、08-09年シーズンのことだ。パラリンピックを目前に控えているにも関わらず、アイスリンクの確保難などから、例年は初夏に行っているトライアウト実施が10月と出遅れた。さらに、選手数名がケガや仕事、家庭の事情などで、次々とチームを離脱。実力を試す絶好のチャンスであったカナダへの2度の遠征も、結局はフルメンバーを招集できずに、満足いく体制で臨むことができなかった。
ようやく中北監督が思い描く代表選手がすべてそろったのが、昨年5月の世界選手権直前のこと。それから現在までの約9カ月間は、2回の海外遠征と12回におよぶ強化合宿を実施。その成果は、とくにこれまで2つ目だったセットの攻撃力の向上という形であらわれ、「チームとしてのまとまりが出てきた。やっと、追い求めていた“理想”に近づいた」と中北監督。
この4年間のなかでは、攻守のバランスが取れたベストの状態に仕上がっていると感じる。世界の頂点をめざした、8年間。その願いを叶えるときが、ついにやって来る。
◆中北浩仁(なかきた・こうじん)/アイススレッジホッケー日本代表監督
香川県出身。6歳でアイスホッケーを始める。中学時代は夏休みのたびにカナダのアイスホッケースクールに通い、卒業後はカナダの高校、さらにはアメリカの大学にホッケー留学した。その後、右ひざの靭帯を断裂し、現役を引退。2002年に、アイススレッジホッケー日本代表の監督に就任。アイスホッケーの戦術と動きを取り入れたチームづくりに着手し、改革を実行した。普段は日立製作所に勤務し、海外を舞台に活躍する国際派営業マンでもある。
(取材・文/荒木美晴、撮影/吉村もと)