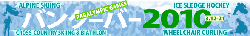車いすラグビーの国際大会「三井不動産 2022 車いすラグビー SHIBUYA CUP」が19日から2日間の日程で、国立代々木競技場第二体育館で開催された。次世代選手の活躍機会を設けようと、日本車いすラグビー連盟が主催する新しい大会で、日本代表とオーストラリア代表が計4試合を戦った。今大会は有観客で実施され、場内音楽や場内解説がついたほか、ハーフタイムにはプロのダブルダッチチームやプロダンスチームがパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。
日本代表の平均年齢は27歳
日本代表の12人は連盟の若手選手を中心に構成。平均年齢は27.0歳で、10月に開かれた世界選手権の日本代表の34.6歳を7.6歳下回っている。キャプテンはその世界選手権に出場した20歳の橋本勝也(日興アセットマネジメント)が務めた。
1日2試合、2日間で計4試合をこなすスケジュール。タフさが求められるなか、日本代表は第一試合から全員が出場。ハイローライン、バランスラインと、さまざまなラインナップが組めるのが強みのひとつで、選手交代を繰り返しながら、それぞれが持ち味を発揮。また、チームディフェンスが機能し、相手に試合開始早々にタイムアウトを取らせたり、40秒以内のトライを許さなかったりと試合をコントロールし、4連勝とした(スコアは第一試合:62-32、第二試合:51-26、第三試合:54-32、第四試合:55-33)。
スターティングラインナップに名を連ねた安藤夏輝(0.5/障がい福祉サービス事業所サンハウス)は、はじめて海外の選手と対戦し、「日本の選手より身体がすごく大きくて、囲まれて動きづらかった」と、率直な感想を口にする。それでも強気を忘れず、「周りの状況を見て、ボールプレッシャーに行くよう意識した」と話すように、相手のミスを誘うディフェンスで勝利に貢献。チーム唯一の持ち点「0.5」のローポインターとして、役割を果たした。
17歳の青木は「海外の選手と試合ができてよかった」

同じく初の国際大会出場となる17歳の青木颯志(神奈川県立高浜高校)は、クラシフィケーション(障がいの程度によるクラス分け)を受け、持ち点が「2.0」から「3.0」に変更になった。青木は「持ち点が変わったことはあまり気にしていない。(はじめての国際大会だが)緊張はまったくなかった。オーストラリアの選手はデカくて、自分から当たりに行っているのにふっとばされた。外国の選手と対戦できてよかった」と、充実した表情を見せた。
また、21歳の草場龍治(NTTビジネスソリューションズ)は、持ち点が「1.5」から「1.0」になった(初日は「1.5」で出場)。
キャプテンという大役を任された橋本は、コート内外で存在感を発揮。「僕はあまり言葉を使って選手をまとめるのが得意ではないので、プレーで示して、こういうラグビーをしようというお手本を見せたいと思っていた。それがある程度はできたかな」と橋本。「最初はことあるごとに、(世界選手権日本代表キャプテンの)池(透暢)さんならどう声掛けするかなと考えていた。でも、そこに囚われすぎると自分のプレーがうまくいかなくなる可能性があるので、僕なりに新しい感じを出していければいいかなと思う」と語り、前を向いた。
オアーHCは「改善点はあるが、パフォーマンスに満足」

日本代表のケビン・オアーヘッドコーチ(HC)によれば、今大会の開催にあたって複数の国に参加を呼び掛けたものの、いずれも予算的な問題もあって実現しなかったが、オーストラリアだけは当初から積極的に参加の意思を示してくれていたという。
強豪のオーストラリア代表は今年の世界選手権を制しており、今回参加した育成チームも同じスタイルを踏襲している。日本もまた、クラブチームや合宿で経験豊富な先輩選手から直接学び、成長する仕組みができつつあるといい、1年半後のパリパラリンピックはもちろん、その次のロス大会に向けた体制づくりを視野に入れる両チームにとって貴重な実戦の場となった。
そのうえで、オアーHCは「今大会は勝つことが目的ではなく、次のレベルにたどり着くための選考の過程である」と話す。「まだ改善すべき点はあるが、日本代表の12人はチームのシステムを理解できていたし、パフォーマンスには満足している。また、会場では音楽がかかっていて、観客や家族が来ていて、メディアに取材されるという環境のなかで、プレーに集中する経験が積めたことは非常によかった」と語り、手ごたえを感じたようすだった。
(取材・文・撮影/荒木美晴)