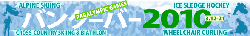目指していた金メダルにはあと一歩、届かなかった。しかしパラリンピックの頂上決戦にふさわしい、すばらしい戦いだった。
車いすテニス女子シングルス決勝が3日、有明テニスの森で行なわれ、第2シードの上地結衣(三井住友銀行)は第1シードのディーダ・デ グロート(オランダ)に3-6、6-7で敗れた。
相手はショットの質も、パワーも戦略も、抜きんでている世界ランク1位の女王。今季の四大大会も3戦全勝だ。「迷わずに打たれるとかなり手ごわい相手。少しでも考えさせるようなプレーが必要」と、上地は序盤から丁寧に深いコースにボールを打ち分け、上から叩かれないよう低い弾道のショットを狙った。しかし、デ グロートは冷静に対応し、隙を見せない。上地の攻撃のリズムに少しずつズレが生じ、思うようにポイントが取れず、第1セットを落とした。
第2セットも我慢の展開が続くが、ゲームが大きく動いたのは3-5と後がない場面から。一段ギアを上げたかのような高い集中力で、上地は第9ゲームで2度、続くゲームでも4度のゴールドメダルポイントをしのぎ、6-5と逆転。次のゲームは落としたものの、タイブレークまで持ち込んだ。一球に魂を込めるように返球していくが、相手のサーブもショットも威力は落ちず、最後は力尽きた。
「要所でプレーの展開を変えたり、やるべき時にやるべきことはできた。これまで負けていた展開とは違ったと思うし、彼女の存在が自分を上のレベルに押し上げてくれたと思う」と、ライバルに感謝する。一方で、「最後は粘れたけれど、そこから相手を突き放すだけの能力が足りなかった」と上地。1時間45分の激闘から成長と課題を得た。
「試合の後に彼女から『いいプレーだったよ』と言ってもらったけど、自分は『ありがとう』より『悔しい』って感じました」と話すと、涙を流した。
デ グロートは前回リオ大会の3位決定戦で上地に敗れている。その悔しさを糧にこの5年間で急成長を遂げ、金メダルを獲得したチームメイト、ジェシカ・グリフィオンの引退と入れ替わるようにオランダ勢のトップに躍り出た。それからの彼女は常に安定した結果を残しており、世界をリードする存在に。上地もパラリンピックの決勝でデ グロートと戦うイメージを持ち続けてきたと言い、準決勝で2大会連続銀メダリストのアニク・ファンクート(オランダ)と対戦しリードされた場面でも、「彼女(デ グロート)と決勝で戦いたいと思ったから踏ん張れた」と振り返る。
技術面で好調だったのは、上地が世界で勝つために磨いてきたバックハンドのトップスピンだ。強い回転をかけたボールは相手コートにバウンドして高く跳ねる。車いすテニスではラケットが届きにくくなるため有効なショットだ。それまで主流だったスライスとは身体の使い方もまったく異なるため、上地はフィジカルトレーニングで身体を作り直し、時間をかけてモノにした。準決勝でも決勝でも、ストレート、クロス、ショートクロスと打ち分け、苦しい場面で自分を助けてくれる武器になった。
盟友、ジョーダン・ワイリー(イギリス)の存在も心の支えになった。決勝前に行なわれた3位決定戦で、前述のファンクートとのフルセットの死闘を制し、銅メダルを獲得した。ワイリーは上地がグランドスラムなどに出場するときのダブルスパートナーであり、親友でもある。
前日に「表彰台の私の隣に並びに来てね」とエールを送られていたといい、「決勝の試合中、何度もその言葉を思い出していた」と上地。「ワイリーにとって今回が最後のパラリンピックになる。だからこそ彼女の隣に行ってあげたかったな」と話すと、また涙があふれた。
車いすテニスがパラリンピックに採用された1998年ソウル大会(この時は公開競技)から、女子シングルスはオランダ勢が席巻し、「9連覇」。そのうち4つの大会で金・銀・銅と表彰台を独占している。しかし、前回のリオ大会では上地が3位に食い込み、そして東京大会ではイギリスと日本の国旗が掲揚された。
「打倒オランダ」は他国選手の重要課題でもあり、「どうやったら勝てるのか、といろんな選手と話すんです。個人競技でライバルだけど目標は同じで、とくにワイリー選手や南アフリカのモンジャニ選手とは『絶対にいつか決勝戦は自分たちで戦おうね』と話しています」と上地。今回もトップの牙城は崩せなかったが、切磋琢磨することでより成熟した世界に進化していくことだろう。
上地は高校3年で出場したロンドン大会がパラリンピック初出場。単複ともベスト8の成績をおさめた。この大会後にテニスをやめるつもりだったが、パラリンピックで国を代表して戦う選手たちの姿に感動を覚え、継続を決意。退路を断ち、プロの車いすテニスプレーヤーの道を選んだ。2014年にはグランドスラムの全仏オープンで初優勝。この年、初めて世界ランキング1位にのぼりつめた。リオ大会では旗手を務め、銅メダル。そして東京大会では、開会式で聖火台の最終点火者をつとめるなど、パラスポーツ界の顔に成長した。
今大会は無観客開催で、多くの人がテレビ放送やオンライン配信で結果を見守っていたが、上地は勝つこと以外にもこんな思いを持って戦っている。
「面白いな、次も観たいなと思ってもらえる試合をしたいという気持ちはいつも持っています。結果を残し続けることが、パラスポーツに興味を持ってもらえるきっかけになると思っています」
今大会の上地の戦いぶりは、映像をとおしても多くの人の心に残るものになっただろう。
競技最終日の4日には、大谷桃子(かんぽ生命保険)と組んだダブルスでも銅メダルを獲得。東京で経験したすべてを、3年後のパリ大会につないでいく。
※この記事は、集英社『Web Sportiva』からの転載です
(取材・文/荒木美晴、撮影/植原義晴)